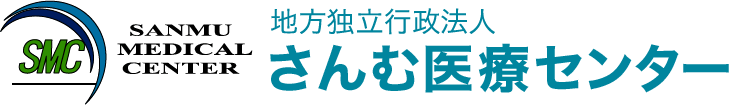検査課
検査課では、医師の依頼により病気の診断、治療の経過など診療上必要な情報を提供するために、様々な検査を行っています。
臨床検査技師16名が「検体検査部門」「生理機能検査部門」「病理検査部門」を分担し、安全かつ精度の高い結果を報告することを心がけています。
全技師が夜間、休日等の緊急検査に24時間対応できる体制を整えています。
また、「日本医師会」「日本臨床検査技師会」「千葉県臨床検査技師会」など各種精度管理調査に参加しています。
検査技師紹介

検査課長
岩﨑 康裕
- 主な担当業務
- 管理・検査全般
有資格者数
臨床検査技師:16名、2級臨床検査士:6名、超音波検査士(心臓領域):1名、超音波検査士(腹部領域):4名、細胞検査士:3名
骨粗鬆症マネージャー:1名、遺伝子分析科学認定士:1名
検体検査部門
患者様より採取した血液、尿など各種検体を検査します。
検査予約患者様の採血は8:00より、採血は採血・採尿受付機にて受付した順に行っています。
取り違い防止の為、お名前の確認を行っています。


血液検査
血球の数、種類等の計測、凝固機能等を検査します。
- 主な検査項目
- 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、血小板数、血液像、PT、APTT、フィブリノーゲン量、FDP、Dダイマーなど


生化学・免疫・血清検査
血液中の成分や酵素、腫瘍マーカー、感染症、免疫機能等の検査をします。
- 主な検査項目
- 電解質(Na、K、Cl)、タンパク質(TP、A/G比、Alb等)、糖質(血糖、Hb-A1c等)、脂質(T-Cho、HDL-Cho、LDL-Cho等)、酵素(AST、ALT、γ‐GT、ALP、LD等)、分解、代謝産物(T-Bil、D-Bil、UA等)、腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、PSA等)、感染症(HBs抗原、HCV抗体、TP抗体、HIV等)


輸血検査
輸血の可否を検査します。
- 主な検査項目
- 血液型、不規則抗体検査、交差適合試験など

細菌検査
病原菌(細菌、ウィルス)の検出、薬剤感受性等の検査をします。
- 主な検査項目
- 一般細菌検査、抗酸菌検査、薬剤感受性検査、ウィルス抗原検査(インフルエンザウィルス、アデノウィルス、RSウィルス、ノロウィルス)など




一般検査
主に尿、便、体腔液(胸水、腹水)、髄液などの検査をします。
- 主な検査項目
- 尿定性、尿沈査、便潜血反応、寄生虫、髄液検査など

生理機能検査部門

生理機能検査部門では医師の依頼により、心電図、超音波検査など各種検査を行います。痛みを伴う検査は殆んど無く、安心して検査を受けて頂けます。正確な検査結果を得るために患者様の協力を得ながら検査を行いますので(体位変換など)ご理解をよろしくお願い致します。わからない事や、不安な事がありましたらお気軽に声をかけて下さい。
検査担当技師に女性技師をご希望の方は、受付に設置されている「女性技師希望」札をご提出ください。なお、検査の順番が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
乳腺超音波検査については全て女性技師が対応しています。
- 主な検査項目
- 心電図、ホルター心電図検査、負荷心電図検査、超音波検査、呼吸機能検査、脈波伝達速度検査(PWV/ABI)
心電図検査
心臓が収縮するごとに、心臓内におこる電気的活動を波形として記録し、その電気信号の乱れから病気の兆候を読み取る検査です。心臓病(不整脈・狭心症・心筋梗塞等)の発見、治療の効果判定、薬の副作用をみるためなどに行われます。
通常、安静時心電図の検査は両手首と両手足、胸に6箇所の電極を取り付けます。この時、手足や肩に力が入ってしまうと筋肉の電気的活動波形(筋電図)が混入してしまうため、身体の力を抜きリラックスして検査を受けていただきます。

ホルター心電図検査
日常生活中の長時間(約24時間分)の心電図を記録して、これを解析する検査です。
不整脈や心筋虚血が起きるかどうか、最高、最低心拍数や不整脈の種類、数、発生時間や心拍数の関係などから、不整脈の診断やペースメーカの機能評価、薬物治療効果などを判定することが出来ます。

負荷心電図検査
運動することで心臓に負荷を与え、運動後の心電図変化を記録する検査です。
マスター2階段試験およびトレッドミル負荷心電図を行っています。

超音波検査
超音波診断装置を用いて腹部、心臓、乳腺、血管、甲状腺等の画像診断を行います。
超音波を検査部位に当ててその反射波を映像化し、臓器の状態や腫瘍などの有無またはその大きさなども調べる事が出来ます。X線検査のように放射線被爆の心配がなく、痛みも殆んど無いため安心して検査を受けることが出来ます。
検査を受けるときの注意点として、腹部を検査する際は絶食の状態で行います。腹部以外の心臓、乳腺、血管、甲状腺等は食事の影響はありません。また、膀胱や前立腺・婦人科領域を検査する場合は尿がたまっているほうが詳しく観察できるので、検査前の排尿は我慢していただく場合があります。

呼吸機能検査
スパイロメータを用い肺から出入りする空気の量や換気機能を調べる検査です。息切れ、呼吸苦、咳、痰が出るなどの肺の病気が考えられる時、呼吸器疾患の重症度や治療の効果判定、気管支喘息の診断補助、手術時の麻酔法の選択の時に行われます。
空気がもれないよう鼻にクリップをつけてマウスピースをくわえ、声に合わせ、口だけで呼吸します。通常、数回行い、一番よいデータを選択します。正確な検査データを得るために患者様に協力していただく検査です。

PWV/ABI検査
両手、両足の血圧の比較や脈波の伝わり方を調べる事で、動脈硬化の程度を数値として表す検査です。この検査を行うことで、動脈硬化の度合いや早期血管障害を検出することができます。

脳波検査
意識障害、頭部外傷、てんかんの診断などを目的とした検査です。脳が活動している時に生じるわずかな電位を測定し脳の働きを調べます。
頭皮にクリームを使い電極をつけ、ベッドに横になり、安静状態で眼を開けたり閉じたり、深呼吸や光刺激などの負荷をかけながらの検査となります。痛みはありません。検査は1時間ほどかかります。

病理検査部門
内視鏡や手術により、患者様から摘出された検体を迅速かつ正確に処置を行い、病理診断を行うことにより、患者様の治療方針を決定する部門です。
標本作製および細胞診診断を臨床検査技師3名が行っています。病理診断を行う病理医は当院には常駐しておらず、現在は国保旭中央病院臨床病理科と保険医療機関連携による遠隔病理診断を行っています。
組織診断
1. 固定
消化管生検標本などの小さな標本は、10%ホルマリンの入った検体ビンにそのまま入れて固定します。
手術標本など切り出しの必要な大きな検体はゴム板に貼り付け、ゴム板ごと10%ホルマリン溶液に漬けて固定します。


2. 切り出し
固定された摘出検体を写真撮影し肉眼所見を記載します。その後、適切に割を入れ、カセットに移します。
大きな検体は旭中央病院臨床病理科とSkypeで接続し、病理医と検体を確認しながら切り出しを行います。


3. 固定包埋
人の組織は水に富んでおり、パラフィン(ろう)とはなじみません。アルコールによる脱水とキシレンによる透徹により標本を疎水性としてから、パラフィンと標本をなじませます。この工程は現在自動化されています(包埋装置)。その後、包埋センターを用いて標本をパラフィンに埋め込み、パラフィンブロックを作製します。


4. 薄切
パラフィンブロックを数ミクロン程度に薄く切り、切片をスライドガラスにのせます。
(数ミクロンとは文字が透けて見える薄さです。)


5. 染色
一般的なヘマトキシリン・エオジン染色を行います。
必要に応じて、特殊染色を行ったり、免疫組織化学染色を外部施設に依頼したりしています。


6. 検鏡
染色されたプレパラートガラスを顕微鏡により詳細に観察し、肉眼所見および臨床情報を総合的に勘案し、病理診断を行います。
病理診断報告書を作成し、依頼元の臨床医に送付します。


細胞診断
細胞診標本は大きく二つに分けられます。一方は婦人科の擦過細胞診標本のように、患者様から採取された検体をその場で直接プレパラートガラスに貼付するものです。もう一方は尿や胸腹水のような液状検体であり、検査室において遠心分離器を用いて細胞成分を沈殿させ、この沈殿をプレパラートガラスに貼付しています。標本を染色し、顕微鏡により詳細に観察し、がん細胞の有無を中心に検索を行っています。


臨床研究・医学教育の為の検査情報・検査試料の利用について
・はじめに
当院検査課で検査されたデータは、各診療科で実施される診療行為のエビデンス(証拠、臨床結果)として使用されるほかに、研究利用(臨床研究、学会報告、精度管理事業、教育等)に利用させていただいております。
・検査情報(検査データ)とは
検査課で検査された各種血液検査材料や標本等、検査数値、心電図、脈波等の波形データ、超音波等の写真、内視鏡検査や手術でとられた組織検体および標本、細胞診検査標本、診断結果などを指します。
・研究利用について
各種検査情報(データ)等を研究利用する際は、既存のデータを利用し、研究の為に患者様の負担となる新たな検査は行いません。
また、各学会等に報告される際は、個人を特定する情報は一切公表いたしません。
現代医療はこれまでの様々な臨床研究の基盤に成り立っており、検査課でもその一助となるべく研究、学会報告を推進してまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
・同意について
検査情報等を研究利用で使用することに同意いただけない場合は下記方法にて検査課へご連絡ください。
未成年の場合は保護者の方にご判断いただき、成人された際はご本人の意思を尊重いたします。
ご連絡ない場合は同意いただいたものとさせていただきます。
同意をいただけない場合であっても、診療行為に影響や不利益はございません。
- 同意いただけない方は、下記の「オプトアウト用紙」に記入後、メールに添付して、
さんむ医療センター検査課のメールアドレスkensa1@sanmu-mc.jpへ送信してください。
又はプリントアウトし記入後、検査課へ持参提出ください。(用紙は検査室にもございます。)
「オプトアウト用紙」はこちら